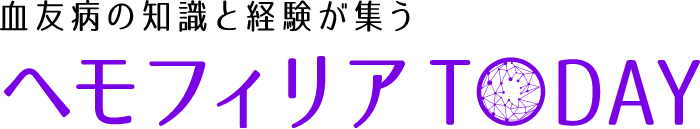みんなの体験談
10代の患者さんに聞きました:
Vol.3 こんなとき、どうしてる?
学校生活のこと
10代の患者さんに聞きました:
Vol.3 こんなとき、どうしてる?
学校生活のこと
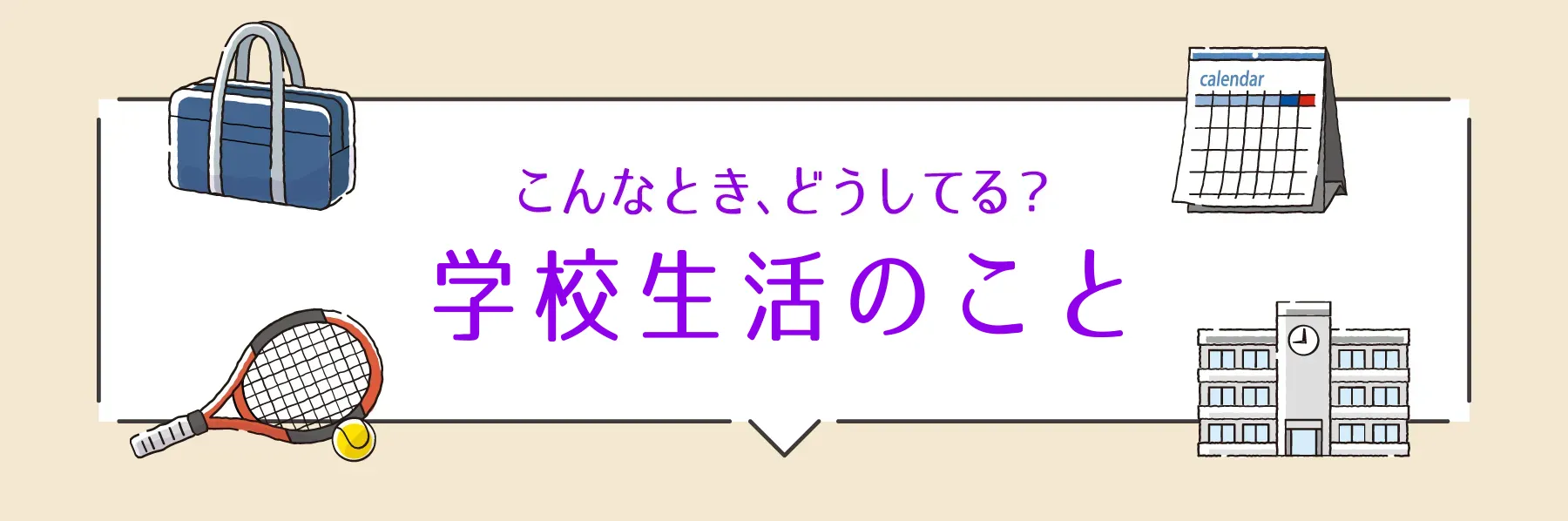
学校生活の中では、周囲に理解されにくい悩みや、部活動での出血への不安など、
さまざまな思いを抱えることもあるでしょう。
けれど、そうした困難を乗り越えた成功体験も、きっとたくさんあるはずです。
学校ならではのさまざまな場面で、患者さんたちは何を感じ、
どのような工夫をしながら過ごしているのでしょうか。
今回は、10代の血友病患者さん4人にお集まりいただき、
学校生活での悩みやそれに対する向き合い方、そしてこれからの夢についてお話をお伺いしました。
聞き手

- 松尾陽子 先生
- (久留米大学病院 小児科)
話し手

- Fさん
- (10代、血友病A・重症)

- Gさん
- (10代、血友病A・軽症)※血友病と診断された女性の患者さん

- Hさん
- (10代、血友病A・重症)

- Iさん
- (10代、血友病B・重症)
※本ページに記載されている内容は、2025年6月14日にリモートにて座談会を実施した際のものです。
目次
周囲の人に、血友病であることをどう伝えたか?

松尾陽子 先生
学校では、血友病という病気のことを周りの人たちにどのように伝えていたのでしょうか?

Fさん
小中学生の頃は、学校への説明は母に任せていましたが、高校生になる頃には自分でも血友病について十分に理解できていたので、自分で説明することが多かったですね。友だちには、血友病のことはあまり話していなかったと思います。もちろん、親しい友だちには伝えていましたが、それほど親しくない人にはわざわざ話すことはありませんでした。

Hさん
自分もFさんと同じような感じです。小さい頃は親に頼っていましたが、血友病との付き合い方がわかってきてからは自分で話すようにしていました。ただ、今は定期補充療法をきちんとしていれば出血は防げる時代なので、血友病であることを誰にでも話す必要はないかもしれません。血友病の当事者と、血友病のことを漠然と知っている人とでは捉え方も違うので、かえって必要以上に心配させてしまうこともあると思います。友だちにも、必要なときだけ話すようにしています。

Iさん
まだ小さかったのであまりよく覚えていないのですが、自分の場合は、小学校に入学したときに、全校集会で血友病であることが児童全員に伝えられるということがありました。たぶん、「病気のことを伝えてもかまわない」とお話ししたからだと思うのですが、まさか全校集会で伝えられるとは、親も予想していなかったようです。もちろん、良かれと思ってしてくださったのだと思いますが、その後、上級生から絡まれたりするといったことも経験しました。親しい同級生だけに伝わっていれば十分だったかもしれません。

松尾陽子 先生
血友病のことを周囲にどう伝えるかはとても重要ですね。周囲が病気のことを理解していれば、患者さんにとってメリットがあることは確かでしょう。しかし今は、Hさんもおっしゃったように、治療をしていれば血友病ではない人と変わらない生活を送ることが不可能ではない時代です。血友病であることを広く伝えることは必ずしも必要ではなく、仲の良い友だちや担任の先生など、関わりが深い人だけに伝えておけば十分なのかもしれないと私も思います。
女性の血友病患者さんならではの悩み

松尾陽子 先生
Gさんは保因者であると同時に、血友病と診断され、現在は血友病の治療を受けていますね。学校生活での困りごとはありましたか?
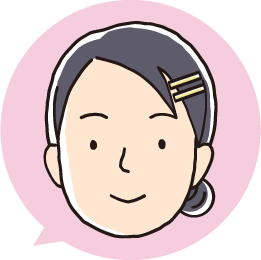
Gさん
私の場合、月経の期間がとても長くて、1ヵ月続いたと思ったら、終わってすぐまた始まり、また1ヵ月続く、みたいな状態だったんです。だからプールの授業などは休んでばかりで、「ズルしてる」みたいに思われたことはありましたね。「生理なら仕方がないよね」と受け取られていたと思いますが、やっぱり少し後ろめたい気持ちはありました。

松尾陽子 先生
同じ女性であっても、月経時の出血が多い人のつらさはそうでない人には理解されにくいものです。そこに保因者や女性血友病という条件が加わると、その大変さはさらに理解されにくくなるのではないかと思います。振り返ってみて、「血が止まりにくい体質だから月経のときも大変なんだよ」と説明しておけばよかったと思うことはありますか?
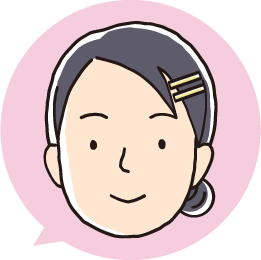
Gさん
昔から出血しやすかったし、月経時の出血についても「こんなものかな」と思っていたので、ことさら周囲に伝える必要はなかったかなと思います。変えようにも変えられないものだし、自分でなんとかしていくしかないなという感覚でした。

松尾陽子 先生
そもそも、Gさんが血友病と診断されたときはどんな気持ちでしたか。
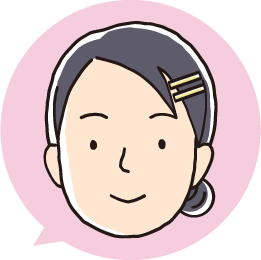
Gさん
落ち込むとかそういう気持ちはなくて、むしろ「嬉しい」という気持ちの方が大きかったかもしれません。というのも、昔から出血しやすくて、生理の症状も重くて(経血量が多い、生理痛がひどいなど日常生活に支障をきたす状態)、婦人科にも通ったけどなかなかよくならなくて、ということがあったので、血友病と診断されたことで適切な治療が受けられるようになり、私にとっては本当にありがたかったです。経済的な負担が軽くなったことも大きかったです。

松尾陽子 先生
それはとても大事なことですね。保因者の中には、血友病患者さんと同じくらい凝固因子活性が低い人もいるのですが、血友病と診断されている人はわずかなので、多くの人が日常的な出血症状に悩まされていると思います。血友病専門医として、もっと保因者の健康に寄り添う医療を提供していかなければと感じています。
血友病の治療を始めてから、苦労は減りましたか?
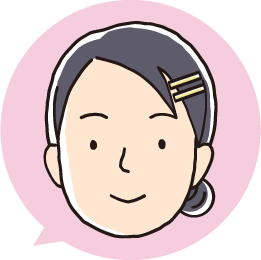
Gさん
かなり減りました。製剤を注射すれば出血は抑えられるので、血友病の治療を始める前と後では症状がぜんぜん違います。

松尾陽子 先生
血友病と診断されたことが、Gさんの生活を大きく変えたと言えそうですね。生理はこの先何十年も続きます。製剤を注射しながら、上手に付き合っていきましょうね。
学校生活の中で、出血対策はどうしてる?

松尾陽子 先生
Fさんはバドミントン、Hさんはスケートボード、Iさんはソフトテニスと、皆さんスポーツを楽しんでいますが、出血に悩んだことはありますか?

Fさん
ときどき出血して、保健室に置いてある製剤を注射することはありました。でも、大きな出血に悩まされることはなかったですね。試合前にハードな練習をしているときでも、特に注射の回数を増やさなくても大丈夫でした。普段の定期補充療法でコントロールできていたと思います。

Hさん
僕も、出血して困ったという経験は特にありません。定期補充療法をしっかり続けていたからだと思います。

Iさん
僕も同じです。先生は心配してくださっていましたが、今のところ出血はなく活動できています。

松尾陽子 先生
皆さん、治療はきちんと続けているからこそ、スポーツを楽しめているんですね。
ちなみに、通院するときは親御さんと行っていますか?

Hさん
病院へは親の車で送ってもらいますが、診察はひとりで受けています。物心ついた頃から、ずっとそうですね。運転免許を取ったら、親に頼らずに通院しようと思っています。

Fさん
自分は小学校3年生か4年生くらいの頃からひとりで通院しています。ちょうど自己注射を始めた頃ですね。製剤の量が多くても、頑張って自分で持ち帰っています。前に通っていた病院は自転車で10分ほどの距離でしたが、今は電車で1時間くらいかけて通院しています。
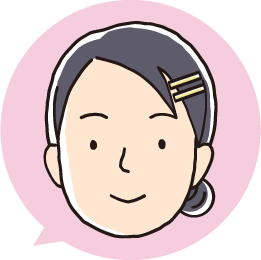
Gさん
私はひとりで通院したことはないんです…。いつも母と一緒に行っています。父が血友病なので、母は病気のことをよく理解していて、診察ではいつも母が先生と話していました。でも、私ももう大人ですし、血友病のことは理解するようになったので、最近は私も先生とよく話します。いろいろな決め事も私自身が判断するようにしています。

松尾陽子 先生
皆さん、自分の意思でしっかりと治療に向き合っていて、本当に頼もしいです。ただ、何かあったときに相談できる相手がいるというのは、とても大切なことだと思います。皆さんは今、独り立ちを始める時期かもしれませんが、親御さんはこれからもずっと、よき相談相手であり続けてくれると思いますよ。
自己注射時のスランプについて

松尾陽子 先生
これまで自己注射を続ける中で、うまく打てなくてイライラしたり、スランプに陥ったりしたことはありましたか?
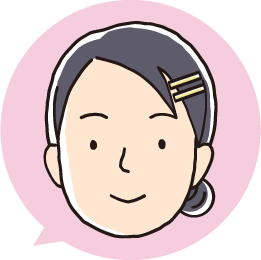
Gさん
利き手が左ということもあり、右腕の外側にしか打てないのですが、血管に針をうまく刺すことができなくてスランプに陥ることがありました。うまくいくときは5分もかからないのに、うまくいかないときは30分くらいかかってしまうこともあって。皆さんは、そういうことありませんか?

Iさん
僕はこれまで、1回だけうまくいかなかったことがあります。そのときは、隣に住んでいる看護師さんにお願いして注射してもらいました。そのくらいかな。右手でも左手でも打てるので、失敗は少ないほうだと思います。

Fさん
自己注射を始めた小学校高学年から中学生になった頃はよく失敗していました。ずっと同じ部位に打っていたので、その部分が硬くなってしまって。そういうときは、母に打ってもらいました。
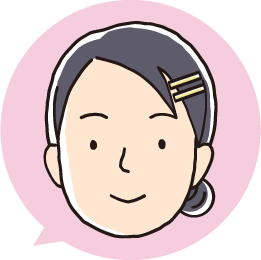
Gさん
看護師さんや先生がわざわざ時間を取ってくださり、「注射を頑張ろう会」を開いていただいたのですが、うまくいかなくて、途中で意識を失ってしまったこともありました。どうしても血管が逃げてしまうんです。注射できる部位が限られているから、その部位が硬くなってしまうこともあって。

Hさん
自分は手の甲に注射していますが、やはり同じ部位にばかり打っているのでその部分は硬くなっています。ただ、血管が逃げてしまったときは、その逃げた血管に位置を合わせて刺すというコツがわかるようになったので、それでうまくできています。
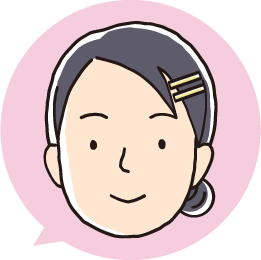
Gさん
製剤の金額を知っているから失敗できないというプレッシャーもあるし、針を刺す痛みもあるし、早くしなきゃと焦ることもあるし、そうした状況が重なって集中できないこともあるんですよね。

松尾陽子 先生
スランプは誰にもあることなので、少し時間を置いて気分をリセットしてからまたチャレンジするのも1つの方法かもしれませんね。いつかはできるようになるから、焦らずに取り組むことが大切です。
将来に対する不安は?

松尾陽子 先生
将来に対して、不安に感じていることはありますか?
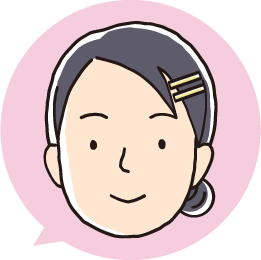
Gさん
私は確定保因者なので、以前は結婚できるのかどうかが心配でした。子どもが血友病の遺伝子を引き継ぐ可能性があるので、それを、相手というよりは相手のご両親がどう思われるかということが気になってしまって。もちろん、私自身が子どもを支えていけるかどうかという不安もありました。

Hさん
血友病の人なら、多かれ少なかれ同じような不安を持っていると思います。自分だけでは決められないことだし。そのときになってみないと答えは出ないことなので。
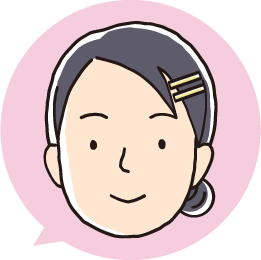
Gさん
そうですよね。それで最近は、あまり気にする必要はないのかなと考えるようになりました。血友病の治療も進歩していて、普通の人と変わらない生活ができるようになっているからです。親も「大丈夫、大丈夫」と励ましてくれます。だから以前ほどの不安は感じていません。

松尾陽子 先生
とても前向きな考えですね。結婚を前向きに捉えることは大切だと思います。きれい事に聞こえてしまうかもしれないけど、そんなふうにしっかりと考えているGさんをひとりの人間として認め、共に家庭を築きたいと思ってくれる人はきっと現れると思いますよ。
将来の夢、親への感謝

松尾陽子 先生
皆さんは将来、どんな夢を描いていますか?

Iさん
まだはっきりとした夢はありませんが、血友病の治療で経験してきたことを活かせる職業に就けたら嬉しいですね。

Fさん
私も具体的には決まっていませんが、情報を扱う仕事や、データサイエンティストのような職業に興味があります。医療系のデータを取り扱う仕事であればなおよいですね。

Hさん
自分は絵を描くことが好きなので、それに関連した仕事ができるといいなと思っています。
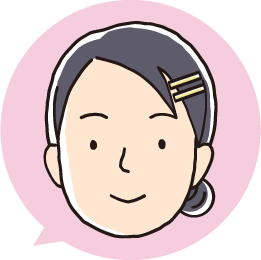
Gさん
私は小さい頃から医療系の仕事に就くことが夢でした。今は医療系の専門学校に通っていて、将来は保健師の資格を取りたいと思っています。行政保健師として仕事ができたら嬉しいですね。これまで、多くの医療者の方々に支えられてきたので、今度は私が「人と医療をつなげる橋渡し」的な役割を担うことができたらいいなと思っています。

松尾陽子 先生
きっと親御さんも、皆さんの将来を楽しみにされていると思います。そこで、これまで育ててくれた親御さんへの思いも、ぜひ聞かせてください。

Hさん
面と向かって言ったことはないのですが、やっぱり、これまで育ててもらったことにはとても感謝しています。

Fさん
小さい頃は半年に1回は足首をケガしていたので、親には心配をかけたと思います。
「ありがとう」のひと言が素直に言えないんですけど、感謝の気持ちはいつも持っています。

Iさん
注射をしてもらったあとに「ありがとう」と言うことはあっても、日頃の感謝を伝えることはないかもしれません。でも、この座談会が終わったら伝えようと思います。
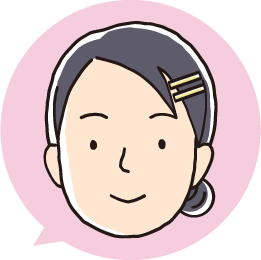
Gさん
診察はいつも母と一緒です。血友病は難しい病気ですし、女性ならではの困りごともあるので、母が一緒に受診してくれることにとても安心感があります。いつも支えてもらっていることに、とても感謝しています。

松尾陽子 先生
親御さんはきっと、これまで毎日、皆さんのことを思いながら暮らしてこられたはずです。血友病であることを受け入れ、やりたいことをできる限りさせてあげたいと願う一方で、出血しないかと日々心配し、将来はどうなるんだろうかと不安にもなり、そうした葛藤の中でずっと支えてこられたのだと思います。だからこそ、照れくさいかもしれないけど、「ありがとう」のひと言を伝えてみてはどうでしょうか。そんな親御さんの気持ちを考えれば、自然と感謝の言葉も出てくるかもしれません。
松尾陽子 先生からのメッセージ
この座談会に参加してくださった皆さんは、血友病と向き合いながら、自分に合った治療を着実に続けているように感じました。だからこそ、学校生活をのびのびと楽しみ、自分らしく過ごせているのだと思います。もちろん、思うようにいかないことやつらい瞬間もあったでしょう。それでも前向きな姿勢で向き合い、今この瞬間を大切にしている姿はとても印象的でした。学校生活を終え、社会に羽ばたいていくこれからも、自信を持って歩んでいくことを心から願っています。