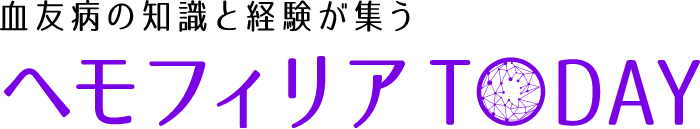2世紀末〜5世紀
ユダヤ教の聖典バビロニア・タルムードが編纂、完成する(現存する最古の「出血しやすい人」に関する記述がある)
血友病とは
【監修】医療法人財団 荻窪病院 血液凝固科
鈴木 隆史 先生
血友病がしっかりと医学的に診断されるようになったのはわずか60数年ほど前に過ぎません。しかしながら有史以来、はるか昔から血友病と思われる「出血性素因」(出血しやすい素因)についての記述や記録が数多くみられます。
ここでは、歴史書物から確認できる血友病の記述から、血友病のしくみの解明や遺伝子の研究が行われた20世紀以降の歩み、そして血友病の治療法の発展について、年表で振り返ります。

ユダヤ教の聖典
バビロニア・タルムード
2世紀末〜5世紀
ユダヤ教の聖典バビロニア・タルムードが編纂、完成する(現存する最古の「出血しやすい人」に関する記述がある)

Albucasis
1000年頃
アラビア人のスペイン宮廷医師である Albucasis が、自身の著書「Al-Tasrif」で、ささいな怪我で出血して亡くなった男性について述べる

Höchstetter
17世紀初め
アウグスブルグの医師 Höchstetter が、出生時に臍出血、その後に鼻血や血便、皮下出血を繰り返す少年について述べる

John Conrad Otto
1803年
フィラデルフィアの医師 John Conrad Otto が、1720年頃の Smith 家系(家系の中で男性だけが出血しやすく、女性を通じてその息子の一部に伝わること)を報告する

Ward
1819年
Ward が患者の血液には凝固のしくみが欠けているという初めての報告を行う
1823年
チューリッヒ大学教授 Johann Lukas Schönlein が、初めて出血者全般に対して「hemophilia」と呼ぶ
1828年
医学論文で初めて「hemophilia」という言葉が使用される
1840年
英国の外科医 Samuel Armstrong Lane が、血友病に対する最初の輸血成功例を報告する
1889年
日本で初めて血友病の疑いがある男の子が報告される
1900年
Landsteiner が血液型を発見する。これにより輸血の安全性が向上する
1902年
日本で初めて血友病の家系が報告される
1911年
Bullock & Fildes が血友病の遺伝について系統的に分析し、血友病の概念を整理し定着させる
Addis が患者の血液に正常な血液から得られた沈殿物を加えると、血液の凝固を補うことができることを発見する
1936年
卵白の成分(臭化抽出物)が血友病に有効であるという論文が「The Lancet」に掲載される
1941年
Lawrence が、凝固因子のはたらきを阻害する物質の存在を報告する
1942年
初めて定期補充療法についての報告が行われる

Pavlovsky
1944年
ブエノスアイレスの Pavlovsky が、患者間の血液を混合すると、血液の凝固を補うこと、つまり血友病は1種類だけではないことを報告する
1947年
Craddock & Lawrence が、凝固因子のはたらきを阻害する物質がインヒビターであると推測する
1953年
2種類の血友病がそれぞれ、血友病 A、血友病 B と呼ばれるようになる
1960年代
奈良県立医科大学小児科の吉田邦男教授が、日本で初めて血友病 B を報告する

ピーナッツ粉末
1960年
ピーナッツ粉末が血友病に有効であるという論文が「Nature」や「The Lancet」に掲載される
1962年
不足している血液凝固因子を、血友病 A では第VIII(8)因子、血友病 B では第IX(9)因子と呼ぶことが決められる
1963年
WFH(世界血友病連盟)が発足する

Judith Pool
1964年
スタンフォード大学の Judith Pool が、ある条件で血漿から生じた沈殿物(クリオプレシピテート)に第 VIII 因子が多く含まれることを発見する
その後クリオ製剤として市販化される(日本では1970 年)
1960年代後半
凍結乾燥した第 VIII 因子製剤や第 IX 因子製剤が使用可能になり、血友病患者の重度出血や手術時の止血が可能になる
1969年
血友病の医療費の一部公費負担制度が始まる
1974年
Cashらが、合成バソプレシンであるデスモプレシンが第 VIII 因子や VWF を増加させる作用があることを発見する
小児慢性特定疾患治療研究事業が開始される(小児の医療費が全額公費負担になる)
1976年
Elsinger がインヒビターのある血友病患者に対する、より効果的な治療を開発する
1982年
Fulcherらが、モノクローナル抗体を用いて第 VIII 因子を高度に純化することに成功する
Kurachiら、Chooらのグループが、第 IX 因子の遺伝子のクローニングに成功する
米国疾病予防管理センター(CDC)によって、血友病患者における初のエイズ患者が報告され、それを受けて製剤の厳重な安全管理が行われる

家庭治療(家庭輸注)
1983年
日本において家庭治療(家庭輸注)が保険適用となる
1984年
米国の Genentech Inc と Genetics Institute の研究グループにより、第 VIII 因子の遺伝子のクローニングが行われる
特定疾病療法制度が開始される(成人も自己負担額が1万円になる)
1990年頃
海外でヒトを対象に遺伝子治療の臨床試験が行われ始める

遺伝子組換え製剤
1992年
初めての遺伝子組換え第 VIII 因子製剤が市販される(日本では 1993 年)
1996年
初めての遺伝子組換えバイパス止血製剤が使用可能となる
1997年
初めての遺伝子組換え第 IX 因子製剤が市販される(日本では 2009 年)
2007年
質の高い臨床試験により、一次定期補充療法が関節障害のリスクを減らすことが確認されたという報告がなされ話題となる
2008年
日本においてヘモフィリア友の会全国ネットワーク(NHNJ)が結成する
日本において C 型肝炎特措法が成立する
2010年
日本において第 1 回全国ヘモフィリアフォーラムが開催される

半減期延長製剤
2014年
日本において半減期延長第 IX 因子製剤が販売される
日本において新たな血漿由来バイパス止血製剤が開発される
2015年
日本において半減期延長第 VIII 因子製剤が販売される