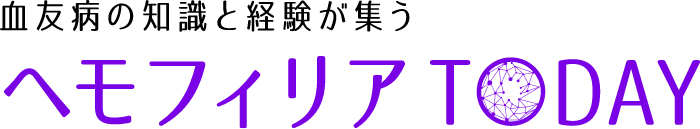治療について
インヒビターとは
【監修】医療法人財団 荻窪病院 血液凝固科
鈴木 隆史 先生
インヒビターとは
インヒビターの正体は、体を異物から守る「抗体」
人間の体には、体内に入ってきたウイルスなどの異物から体を守るための「免疫」というしくみが備わっています。免疫のはたらきの1つとして、異物に対して「抗体」と呼ばれる物質を作って異物にくっつき、異物の活性(はたらき)を失わせる反応を起こします。
ウイルスなど体に悪さをするものに対して免疫がはたらき、抗体ができるのは望ましいことですが、厄介なことに、体にとって必要なものに対しても抗体ができてしまうことがあります。実際に血友病患者さんたちが補充療法で体内に入れている血液凝固因子に対して、この抗体ができることがあり、これを「インヒビター」と呼びます。
もともと血友病患者さんの体内には、血液凝固第VIII(8)因子または第IX(9)因子が不足しているので、補充療法でその血液凝固因子を体内に入れると、体がそれを本来体内に存在しない異物と認識してしまうことがあるためです。
インヒビターがあるかどうかはベセスダ法で検査する
インヒビターができてしまうと、血液凝固因子を補充してもその効果が失われ、出血が止まりにくくなります。インヒビターがあるかどうかは、ベセスダ法と呼ばれる血液検査で調べることができ、インヒビターの量・強さ(力価ともいいます)を表すベセスダ単位(BU)*が用いられます。通常0.6BU/mLを超えた場合、インヒビター陽性と判断されます。
*1BU/mLは凝固因子活性を半分(1/2)にする力価。力価が1増えるたびに、凝固因子活性は1/2に減る。インヒビターのできやすさ・できる力価は人それぞれ
インヒビターのできやすさは人によって違います。家族や親戚にインヒビターができた人がいる場合や、凝固因子活性が1%未満の重症の人に、また血友病Bよりも血友病Aの人にできやすいといわれています。確率でいうと、過去に凝固因子製剤による治療をしたことがない人で、重症の血友病Aでは21〜32%、重症の血友病Bでは9%の人にインヒビターができるといわれています1)。
また、できるインヒビターの力価も人によって異なります。5BU/mL 以上と多くインヒビターができてしまう人を「ハイレスポンダー」、インヒビターができても5BU/mL 未満と少ない人を「ローレスポンダー」といいます。
インヒビターができたら「中和療法」か「バイパス療法」
インヒビターができた場合、これまでと同じ補充療法では止血効果が得られないため、他の治療法が行われます。この治療法には「中和療法」と「バイパス療法」の2つがありますが、「ハイレスポンダー」か「ローレスポンダー」か、そして現在のインヒビター力価によって、治療法を変える必要があります。
中和療法
これまで使っていた凝固因子製剤の量を増やす方法で、主にローレスポンダーや現在のインヒビター力価が低い場合に行われる治療法です。止血に必要なこれまでの量に加えて、インヒビターで失われてしまう量を合わせて投与します。
バイパス療法
第VIII因子や第IX因子を使わずに、第VIIa因子など、別の凝固因子を使って止血する方法です。主に、ハイレスポンダーや現在のインヒビター力価が高い場合に使われる治療法です。