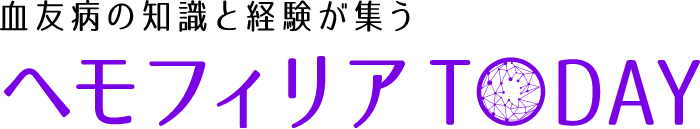治療について
血友病患者さんでは血液凝固第VIII(8)因子または第IX(9)因子が不足したり、はたらきが悪くなっていて、出血したときに血が止まりにくくなっています。このはたらきのことを「活性」といいます。そのため治療法として、「補充療法」といって不足している血液凝固因子を補う方法が行われています。
しかし、血液凝固因子は体の中に一度入れてしまえばOKというわけにはいかず、入れても徐々にその量が減ってしまう性質があります。例えば一般的に、第VIII因子であれば8〜14時間、第IX因子であれば16〜24時間経つと、血液中のそれぞれの血液凝固因子の活性は半分になってしまいます1)。この活性が半分になってしまうまでの時間を「半減期」と呼びます。
血液凝固因子をどのタイミングでどのように補充するかは出血の具合や、人それぞれの生活、補充する血液凝固因子の半減期などによって異なっていて、主に血友病の補充療法は3つの方法に分けることができます。
1) 日本血栓止血学会:インヒビターのない血友病患者に対する止血治療ガイドライン 2013年改訂版